生命機能をデザインし社会課題解決に挑む


大阪大学大学院工学研究科 教授
青木 航
生命科学の可能性に魅せられて
幼少期からサイエンスは楽しいものだと感じていました。「地球が太陽の周りをまわっている」といった、子どもの素朴な日常感覚を覆されるような話を親がたくさんしてくれた影響で、自然と科学にひかれていったのだと思います。両親が博士号を持っていたため、研究職は一番イメージしやすい職業でした。親のアドバイスをきっかけとして生物学の道を選び、学部4回生で研究室に配属されて以降、生命科学の面白さに目覚め始めました。
現代生命科学の最も重要な革命は、1953年のワトソンとクリックによるDNA二重らせん構造の発見です。その後次々と生命のルールブックが解明され、私が研究に取り組み始めたころには、生命とは何か?という根源的疑問に対する大まかな答えは明らかになりつつありました。では、それで生命科学はエキサイティングではなくなったのかというと決してそうではありません。むしろベースが明らかになったことで生命を自由自在にエンジニアリングできる時代になったのです。エンジニアリングで新しい生命機能をデザインし、それが社会課題を解決する大きなブレイクスルーになることに、私は生命科学の面白さを見出しました。例えば、発酵による有用化合物の大量生産や、抗体医薬や細胞医薬による医療の革新など、生物学が世界を変えるツールになってきています。工学部で生物を自由自在にエンジニアリングしていく研究分野は、これから50年100年先もエキサイティングなんじゃないかなと思います。
ライフワークとして、社会を変革するバイオテクノロジーを追求
人生で自分が一番楽しいなと感じることがサイエンスです。この世界にそれ以上に夢中になれるものは存在していなくて、そういう意味で、裁量労働制の大学教員という働き方はハッピーな環境です。大阪大学で研究室を主宰するという極めて貴重な機会を頂き、社会を変えるバイオテクノロジーの創出に向けて今後は全力で取り組んでいきたいと考えています。
今は創薬を変えるような新しい基盤技術の確立にチャレンジしています。薬の開発には、技術の提案から臨床試験、上市まで20年かかるため、最終的な成果が見えてくるのは60歳になるころでしょうか。その長い道のりを進むため、同じ夢に向かって一緒に熱く取り組んでくれる仲間のチームアップに力をいれているところです。SNSもチームアップに役立っていて、実際にSNSがきっかけで繋がった企業の方と現在進行形でプロジェクトを進めています。情報があふれる時代だからこそ、「青木航という人間がここにいて、楽しそうなことをやっている」と自ら発信することが大事だと感じています。研究は自分にとってライフワーク。科学の面白さを発信しながら、社会を変革するバイオテクノロジーに挑戦し続けていきたいと思っています。
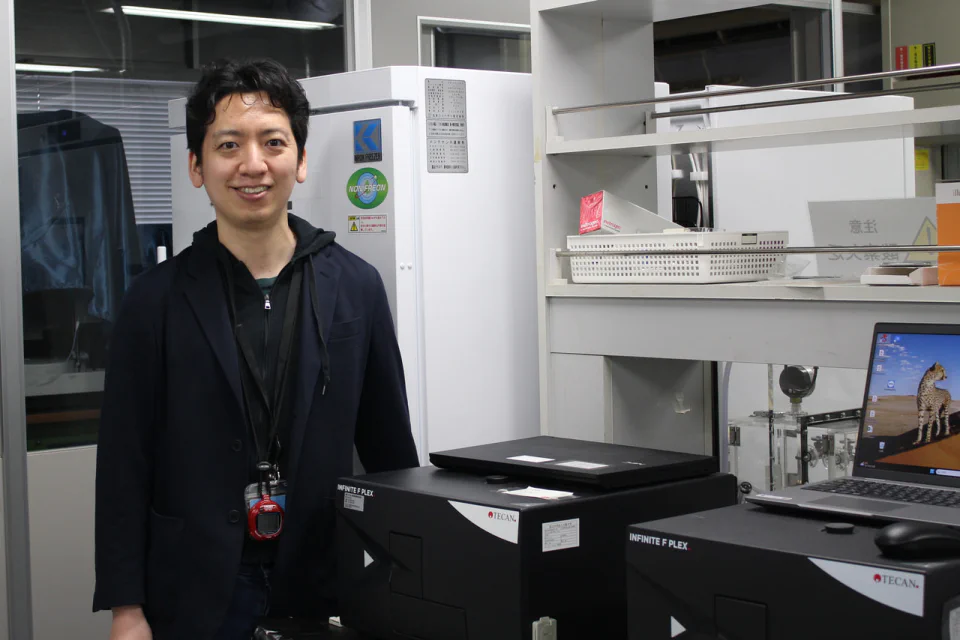
自分の人生を楽しめる領域を見つけて
若手研究者の方や学生の皆さんに向けて、私が大事にしている二つの軸をお伝えしたいと思います。まず一つ目は、「心身の健康が最も大切ということ」です。自分の心身は唯一無二のもので、それが最も大事な資産。それを壊さないように研究に取り組める環境こそが一番重要だと考えています。
もう一つの軸は、「楽しく取り組む」ということ。興味やモチベーションは、何かを成し遂げるための重要なドライビングフォースだと思います。自分がやりたくないことを続けるのは難しいものです。それでもやらなくてはいけないことは世の中にあるけれど、自分のやりたいことと研究テーマがマッチした時のパワーってすごいと思うんです。だからこそ、ぜひ自分がエキサイトできるような研究テーマを見つけてほしい。そのために、学部の時からいろんな研究室を見ると良いと思います。研究インターンシップやアルバイトなど実践プログラムもありますし、早い段階から幅広い選択肢に触れて、自分に合うものを探してみることも大切だと思います。
そして、キャリアパスの選択肢は無限に広がっていることも伝えたいです。修士号や博士号(Ph.D.)を取得した後、皆さんのキャリアは無限に広がっています。私の身近な例でも、専門知識を使って翻訳家になったり、国連で働いたり、さまざまなケースがあります。私自身はたまたまアカデミアで研究職をするのが楽しかったのでこの道を選びましたが、そもそもPh.D.というのは一人前の科学者としての素養を持つことを示す資格にすぎません。社会はさまざまな領域のスペシャリストがチームとなって価値を生み出しています。自分の基礎的能力や専門的知識を活用しながら、楽しめるキャリアをぜひ見つけてほしいと思います。
コラム
Column
印象に残っている旅先は?
20年位前に訪れたアムステルダム。良くも悪くも自由度が極めて高いところにカルチャーショックを受けました。次に、ニューヨーク。文化の密度がすさまじく、マンハッタンの限られた空間に美術や舞台芸術など様々なものが重層的に連なっている様子に感銘を受けました。そして、ジュネーブのCERN。人類の科学の到達点の一つだと思います。
ストレス解消は?
サイエンスを考えること自体がストレス解消です。アイディアを生み出すにはどれだけ既存の知識を持っているかが大事なので、通勤電車の中では論文を読んで知識をインプットしています。昔からアイディアが浮かぶのは、馬上、枕上、厠上、といわれていますが、私は枕の上。こんなこともできるかもと閃くと起き上がってメモを取るのですが、その瞬間が楽しいです。
プロフィール
Profile
青木 航 AOKI Wataru
大阪大学大学院工学研究科 教授
博士(農学)。京都大学大学院農学研究科助教を経て、2023年大阪大学大学院工学研究科教授に就任。現在に至る。
掲載日:2025年3月21日/取材日:2025年2月5日 内容や経歴は取材当時のものです。
関連リンク
Related Links


お話を伺って
人との関わり合いと研究へのモチベーションについて熱心に語ってくださった青木先生。自分が楽しいと思うこと、またそれをともに楽しむ人と一緒に進んでいくその姿勢から新しい生命機能が創造されるのだと感じました。(吉澤、古谷)