究極の予測技術で世界の人に貢献したい
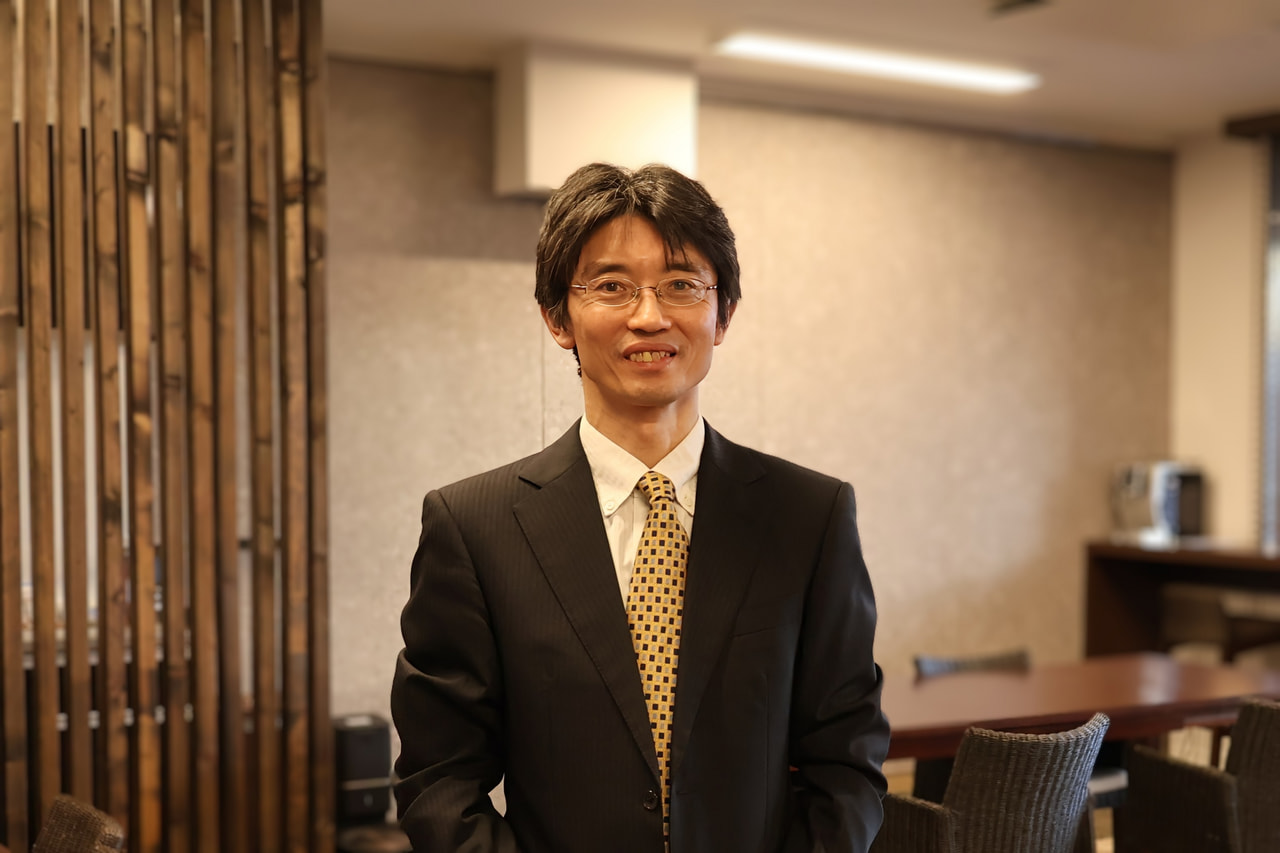

大阪大学産業科学研究所 教授
櫻井 保志
「これがあれば」を形にしたい ― エンジニアから研究者への転身
大学卒業後、情報・通信企業に就職しました。そこでは、顧客の要望をもとに開発したシステムを納品する、今でいうITコンサルタントのような仕事をしていました。そこで多くのお客様から、事故発生を防ぐために常にデータをとって予測できるような技術はないか、という声をいただいたのですが、当時はまだそうした技術は存在しておらず、ならば自分で作ってみようと思ったことが、研究への入り口となりました。働きながら大学院で学び、希望して同企業の研究所へ異動。博士号を取得し、本格的に研究者として歩み始めたのは、30歳の頃でした。
一般的に研究者はNatureなどのトップ学術雑誌を目指しますが、情報分野ではトップ国際会議での発表がより重視されます。企業勤務の私にとってそれは高い壁でしたが、日本の学術誌に論文が採択され研究者としての自信を得た頃に、思い切ってトップ国際会議への投稿に踏み切りました。ところが、「これはもはや論文ではない」と酷評されあっさり却下。それでも「必ず通してみせる」と心に決め、めげずに挑戦を続けました。毎日、仕事終わりに研究所の裏手の三浦半島が見える海風が強い場所に行き、「明日も頑張るぞ!」「必ず通すぞ!」と暗い海に向かって叫んでいましたね。そんな日々が続いたある日、トップ国際会議からメールが届き、開いてみるといつもの “Unfortunately”ではなく“Congratulations”の文字が。あまりにも嬉しくて、その場で叫び出したい気持ちをなんとかこらえ、また海へ。昼間だったので、周囲に誰もいないのを確認して「やったー!!」と叫びました。あの瞬間は、人生で最高に嬉しかった出来事のひとつです。しかもその後、世界中から「プレゼン資料を送ってくれ」「ソースコードを送ってくれ」とメールが殺到してとても驚き、良い研究をするのは本当に素晴らしいことだと実感しました。
未来の予測によって社会を変革する
大学に転職後のことですが、企業の方との会話を通じて、パソコンを不要とし、小型デバイスや組み込み機器で動作する軽量・高速・省メモリの予測技術の必要性に気づきました。そして、そうした技術を日本の産業の強みや特性と結びつけて活かせないかと考えました。そこで、まずは製造業におけるセンサーデータ活用、いわゆるIoT領域に着目し研究開発を進めることに。さらに、日本は世界に先駆けて高齢化が進む国です。医療現場でもデータ解析が役に立つだろうと考え、医療AIにも取り組むようになりました。こうした分野に貢献するため開発したのが、従来のビッグデータ型の深層学習とは異なり、小さなデバイス上で即座に学習・予測できるリアルタイムAI技術です。「未来の予測によって社会を変革する」を研究理念に掲げ、この世界初・世界最速の技術で、社会に貢献したいと考えています。
この研究への熱意は、研究室運営にも息づいています。私の研究室では、企業と連携しながら実用的な研究を進める一方で、AIやデータ解析分野のトップ国際会議への論文投稿にも挑戦していて、学生たちには常に「一番高いところを目指そう」と声をかけています。ただし、社会的インパクトのある実用的な研究と、アカデミアにおいて評価される研究は必ずしも一致しません。そこで、学生のうちは論文を国際会議に通せる力を養い、博士課程修了後、助教になる頃、もしくは企業の研究所に就職する頃には革新的な技術を生み出せるようになるよう指導しています。このような育成方針は、カーネギーメロン大学留学時代の経験に基づくものです。企業在籍中に、データ解析の第一人者であるChristos Faloutsos教授のもとで研究する機会に恵まれたのですが、そこで、博士課程の学生がラボに入ってから4、5年でトップリサーチャーとして成長していく姿を目の当たりにしました。最初は丁寧に伴走しつつ、徐々に学生の裁量を広げ、最終的には自らテーマもコラボレーションの相手も決められるように導いていく。その指導法に深く感銘を受け、私自身も大きく影響を受けました。今、私の研究室でもその育成スタイルを実践しています。

まだ誰も手をつけていないテーマは星の数ほどある
研究は、定年を迎えても続けられる仕事です。ですから、研究職を目指す人には、漠然とした感じでもいいので「こういうことが実現できればいいな」といった自分なりの人生の目標を持ってほしいと思います。そのうえで、1年単位や日々の目標を立てて、一歩ずつ進んでいくといいのではないかと。難しいのは、夢というのは実力がないと見つからない、ということです。小学生の頃に自由に描くような夢とは異なり、大人の夢は力をつけて初めてその輪郭が見えてくる。ですので、人生の目標を持ちつつ、力をつけながら、少しずつ自分の夢を形にしていけばいいのではないかと思います。
そして、社会にとって重要なのにまだ誰も手をつけていないテーマは、実は星の数ほどあるということもお伝えしたいです。「こんなものだろう」と現場で見過ごされている課題を、テクノロジーの力で大きく変えられる可能性は無限に広がっています。流行に流されず自分の目で社会を見て、「何か役に立てることはないか」と問い続ける。そうすれば、きっとあなたにしか見えないテーマが見つかるはずです。さまざまな評価軸がありますが、仕事の価値は、誰かの役に立ったかに尽きると思います。まだ世の中にない技術で、誰かの「これが欲しかった」を実現できたら素晴らしいですね。
コラム
Column
好きな場所は?
子どもを預けている保育園。いろんなお子さんとおしゃべりするのですが、子どもって常に何か面白いことを探しているのです。何者にもなれる雰囲気があって、素晴らしいです。もちろんトラブルもあるとは思いますが、子どもたちは何かあってもすぐに忘れて「これ楽しいよ」という感じで、未来はいいことしかないと思っているように見えて。そんな様子を見るのが、私はすごく好きです。
プロフィール
Profile
櫻井 保志 SAKURAI Yasushi
大阪大学産業科学研究所 教授
博士(工学)。1991年 日本電信電話株式会社(NTT)入社。1996年 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了、1999年 同博士後期課程修了。2013年熊本大学教授を経て、2019年より大阪大学産業科学研究所教授。2020年より同産業科学AIセンター センター長。現在に至る。
掲載日:2025年9月11日/取材日:2025年2月21日 内容や経歴は取材当時のものです。
関連リンク
Related Links


お話を伺って
研究室の共有スペースがとても素敵で、思わず学生さんたちがうらやましくなりました。「こんな研究室があったらいいな」という先生の理想が、そのまま形になっているようです。対話を大切にされているとのことでしたが、あの環境なら会話も弾みそうだと感じました。取材は和室で行われ、そこもまた落ち着いた素敵な空間。私たち取材チームは慣れない正座で早々に足がしびれてしまいましたが、先生は1時間ほどの取材中も姿勢を崩すことなく変わらぬご様子。その佇まいから先生の内に秘めた芯の強さが伝わってくるようでした。(古谷、岸本)